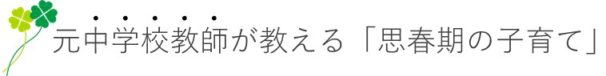怒りの取り扱いアドバイザー・元中学校教師いなっち先生こと稲田尚久です。
「これぐらいのことができないと社会では通用しません」
これって、本当にそうなの?
教師や親が子どもへ言うのは正論とは言い切れない
例えば、友達の宿題を丸写しで提出する子どもがたまにいますよね。
教師は宿題チェックをすれば、すぐ見抜きます。
そんなとき、よく聞く言い方。
「こんなことしてもあなたのためにならないし、社会に出てからは通用しません!」
「この程度の宿題の提出期限が守れないようじゃ、社会では通用しません!」
どうなんでしょう?
宿題の提出日に間に合わせたいから、苦肉の策で友達に頼んで見せてもらった。
これはこれで、子どもの生きぬく力なんじゃないかな?
(もちろん宿題を写すことを全面肯定しているのではありません)
社会に出たとき、突発的な場面に出くわすことってありますよね。
そんなとき、いかに上手に切り抜けていけるか?
こういう力って大切だと思うんです。
もちろん、法を犯すような切り抜け方はダメですよ。
法に触れるという状況でないなら大切なことです。
『嘘も方便』っていうじゃないですか。
思春期になれば嘘やズルも経験しながら成長する
子どもが嘘をついたり、ズルをしたとき、親や教師はすべて叱る必要はないと思います。
人を傷つけるような人権に関わることは、厳しく叱る。
そうじゃないことならば、見逃すのもありです。
ただし、気をつけておかなくてはいけないのは、ウソをつかなければいけない状況に追い込まれた子どももいるということ。
これが一番問題ですよ。今回はそうじゃない場合についてです。
さて、子どもの嘘を見逃すときのコツがあります。
「先生はわかっているよ」
「親は気づいているよ」
という態度をときどき匂わせておくことですね。
例えば、先ほどの宿題丸写しの場合
「あなたの宿題、A君の宿題をまるでコピーしたみたいだったなあ。もしかして透視能力あるんじゃない?」
とか
「昨日の宿題を友達のを見て、きれいに写した人がいました。あんなにきれいに写せるなんて感心したなあ。でも、提出点はその人0点だけどね」
と、先生は見抜いてますよってところを匂わすんですね。
生徒の表情は「ヤベッ!」ってなったりします。
子どもは経験をし大人になって気づく
「ヤベッ!」と思えば、もう充分。
次からは、これは通用しないと気づきますからね。
教師や親が正論を振りかざしすぎない。
僕は大切だと思いますよ。
大人になった教え子からこんなこと言われたことがあります。
「先生、実はあのとき嘘ついてました。すいません」
自分の中で「しまったなあ」という後悔があったのでしょう。
人はそう思うと、どこか心の片隅に重荷を抱えたままになります。
それを言えた時、次へ進めますよね。
それが成長なのだと思います。
教師や親がすることは「いつか気づいてくれる時が来る」と信じてやること。
子育ても教育も長い目で見てやることが必要ですね。
でも、日々いろんなことを子どもは起こします。
それに対して、「怒る必要があるのか?」「怒る必要がないのか?」を、教師や親は適切に判断できるスキルを身につけたほうがいい。
「これぐらいのことができないと社会では通用しません」
と、子どもへ言う前に、教師も親も感情コントロールくらいできないと、社会では通用しませんよ(笑)
アンガーマネジメント、コミュニケーション、子育て
子どもから大人まで、岡山発どこへでも
研修や講演のご相談はお気軽にどうぞ!
数人の子育て座談会から企業研修まで対応
企業での社員カウンセリングも対応